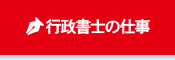よくある質問
民事関係
 1
1- 「内容証明」とは何でしょうか?どんなときに出すのでしょうか?

- 「内容証明」とは、郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明することで、法的な証拠付けになり得るため、クーリングオフの場合など、各種通知書や催告書などを出す場合に使います。
ただし、内容証明は証拠付けになっても、法的強制力はありません。
また、場合によっては、むやみに内容証明を出すと相手の態度を硬化させることにもなりかねません。出す場合には行政書士に相談されることをお勧めします。
 2
2- 「公正証書」とは何でしょうか?どんなときに使いますか?

- 公正証書は、公証人が法律に則って作成する公文書で、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の賃借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに関する公正証書などがあります。
公正証書は証明力が高く、強い執行力を持ちます。債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
どんな場合に公正証書にした方がいいか、どんな場合に公正証書にしなければならないかについては、行政書士にご相談ください。
 3
3- (消費者契約法)どのような契約が対象になりますか?

- 消費者と事業者の間で締結される契約(労働契約を除く)の全てが対象となります。
この場合に「事業者」とはすべての法人及び「事業として又は事業のために契約の当事者となる」個人をいいます。
また「消費者」とは前記以外の個人をいいます。ですから、消費者が個人の場合であっても、事業のためにした契約は、消費者契約法の対象になりません。
 4
4- (消費者契約法)どのような契約を取り消すことが出来ますか?

- 契約を勧誘する事業者に以下のような不適切な行為があり、それによって契約をした場合は取り消すことができ、大きく分けて次の2つのケースがあります。
- 事業者の情報提供が不適切なため、消費者に「誤認」を生じた場合
- 事業者が重要事項について真実と異なることを言った。(不実告知)
- 将来の見込みを断言した。(断定的判断の提供)
- 消費者に不利益なことを知っていて隠していた。(故意の不利益事実の不告知)
- 消費者による不当な強い働きかけがあり、消費者が「困惑」した場合
- 自宅や職場に来て帰って欲しいと言ったのに居座って契約を結ばせた。(不退去)
- 呼び出されて帰してもらえず契約を結んでしまった。(監禁)
- 事業者の情報提供が不適切なため、消費者に「誤認」を生じた場合
 5
5- (消費者契約法)契約の取引以外に、消費者の救済方法はありますか?

- 事業者の定型的な契約書(及び約款)を使用するような場合、契約の内容が消費者の利益を一方的に害するとき、消費者契約法は、その条項を無効とするとしています。
例:法外なキャンセル料を要求するもの。事業者の損害賠償責任を免除や制限しているものなど。
 6
6- (消費者契約法)いつまでに取消をすればいいのでしょうか?

- 取消権は誤認に気がついたとき又は困惑行為のときから6ヶ月、契約成立後から5年以内であれば行使できます。
 7
7- (消費者契約法)契約の取消はどうすればいいのですか?

- 取消の意思表示は、口頭による場合でも有効ですが、取消の意思表示と日付を明確にするためには、内容証明郵便等により、書面で事業者に通知する方がいいでしょう。(Q2参照)
また、紛争になった場合、取消の理由は消費者側が証明する必要があるので、契約書、パンフレット、説明資料や説明を受けた時のメモなどは大切に保管しておきましょう。
 8
8- (特定商取引法)「クーリング・オフ」はどんな場合にできますか?消費者契約法による契約の取消とどう違うのですか?

- 訪問販売、電話勧誘等不意打ち的勧誘により商品や役務(サービス)を購入した場合、契約書を受け取った日から8日以内(マルチ商法、内職・モニター商法は20日以内)であれば、原則無条件で契約の申込の撤回または契約の解除ができること(クーリング・オフ)が、特定商取引法などで定められています。一部の例外を除き、原則全ての商品と役務(サービス)が対象となります。
じっくり考えてから購入できる店舗での買い物や通信販売には、クーリング・オフは適用されません。誤認、困惑の理由がある場合は、消費者契約法による取消ができます。通信販売の場合は、事業者が独自に契約や返品のルールを設けている場合があり、契約前に返品ルールの有無と、その内容をよく確認しましょう。
 9
9- (特定商取引法)訪問販売がしつこく、断りにくくて困っています。

- 訪問販売では、消費者が契約しない旨の意思表示をした場合は、それ以上勧誘してはならないことが法律に明示されています。はっきりと断るようにしてください。
 10
10- (特定商取引法)判断能力が不十分な高齢者が訪問販売で勧誘されるまま、たくさんの布団を購入しました。解約できるでしょうか?

- 訪問販売では、その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約は、契約締結から1年間、契約の申込の撤回又は売買契約の解除ができます。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があったとみなされるとできません。
 11
11- (賃貸借)借家の修繕をしたいのですが、家主さんに修繕費用を持ってもらえるのでしょうか?

- 民法では、賃貸人は賃貸物の使用をするのに必要な修繕をする義務があると規定しています(民法第606条)。借家人は修繕の必要なその旨を家主に伝えたうえで(民法第615条)、家主に修繕を求め、自ら修繕費用を出したときは家主にその償還を請求できることになっています(民法第608条)。
一般的な修繕費用の負担基準としては、建物の主要構造部分(柱、屋根、壁、床、基礎土台など)については、家主に修繕義務があるとされ、建物の付属部分(畳、建具、ふすまなど)は借家人に修繕義務があるとされています。
しかし、特約等により借家人が修繕義務を負うとされている場合などもあり、そのようなケースでは個別事案ごとに判断が必要になります。
 12
12- (賃貸借)マンションを出ることになりましたが、家主さんが敷金を全額返還してくれません。どうしたらいいでしょうか?

- 敷金とは、家主にとっては、借家人が借りた部屋を明け渡すまでに生じた一切の債権を担保する金銭のことをいいます。敷金は通常、入居日までに家主側に差し入れ、契約期間が終了し明け渡しを完了した後、「未払い家賃」や「原状回復費用」を差し引いた上で、返還されます。
法的には、敷金は家主が借主から「預かっている」にすぎないものですから、「未払い賃料」や、借りた部屋を故意・過失により汚したり破損したりがない限りは、「全額」返還されるのが原則です。ただここで、最もトラブルの原因となりやすいのは、「原状回復費用」について両者の言い分が違うことです。話し合いがつかない場合は、専門家にご相談ください。
 13
13- (賃貸借)賃貸借契約に特約として、敷金が全額返還されない条項が含まれていた場合は、それに従わなければならないのでしょうか?

- 敷金のうち、一定金額を差し引く制度を敷引きといいますが、敷金は全額返すのが原則であることを考えれば、敷引きの特約があるからといって、必ずしも家主は敷金返還義務を免れるわけではありません。
特に、借家人の過失の有無に関わらず敷金は一切返さない旨の特約は、消費者契約法に反し無効とする最近の判決もあります。たとえ家主が個人であっても、反復継続して賃貸マンションを経営している場合には、消費者契約法の適用があります。
 14
14- (委任状)委任状の作成をする際、特に注意すべき点はありますか?

- 委任する事項の内容をできるだけ明確(具体的)にすることです。白紙委任状の作成は避けてください。
 15
15- (契約書)契約書を作るとき、捨印をして欲しいと頼まれました。どうしたらいいでしょう?

- 改竄防止のために、避けるべきです。
 16
16- (保証)友人の金銭消費貸借契約の保証人になって欲しいと頼まれました。保証人には誰でもなれるのですか?また、一旦保証人になった後、気が変わった場合は保証人をやめることはできますか?

- 保証人とは、債務者が立てる場合は、行為能力者で弁済能力があれば、基本的には誰でもなれます。(民法450条)
保証をすれば、金銭消費貸借契約に付随的に、債権者と保証人との間に保証契約が成立します。保証契約締結後は、原則として、債権者が同意するか、弁済が終了するかしなければやめることはできません。但し、債権者側に詐欺や脅迫があった場合は、保証契約を取り消して保証人をやめることが出来る可能性があります。(民法96条1項)
 17
17- (保証)保証人と連帯保証人の責任に違いはあるのですか?

- 責任に違いはありません。どちらも主たる債務者の債務を保証することに違いはありません。(民法第446条)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべきであるということができ(催告の抗弁権 民法第452条)、また、債権者がこの規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済する資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければなりません(検索の抗弁権 民法第453条)。
一方、連帯保証人にはこれらの抗弁権がなく、債務者と同じように債務の履行の請求を受けます。
 18
18- (保証)友人の賃貸借契約の保証人になろうと思いますが、注意する点はありますか?

- 一般に、賃貸借契約においては、連帯保証人になる場合が多いです。連帯保証人となる人も、賃貸借契約および保証契約の内容を十分に理解した上で判断してください。
 19
19- (自転車事故)歩道を歩行中、自転車がぶつかってきて怪我をしました。警察に届けるべきでしょうか?

- 人身事故の場合、どんな小さな事故でも、加害者は警察に届け出る義務があります。自転車と歩行者の場合、自転車搭乗者が届け出ない場合もあり、被害者が届け出を出した方がいいと思います。
自転車と歩行者の事故や、自転車同士の事故により、歩行者等を死傷させた場合、自転車利用者に過失または重過失があるときには、業務上過失致死傷罪が課せられることがあります(刑法第211条第1項)。
 20
20- (自転車事故)自転車と歩行者の事故の場合で過失割合はどのようになるのでしょうか?

- よくホームページなどに、自転車と歩行者の過失割合について、何%対何%などど載っていますが、参考程度にしてください。事故の状況で、ひとつとして同じ事故はなく、ケース・バイ・ケースです。
過失割合については、信頼のおける専門家にご相談ください。